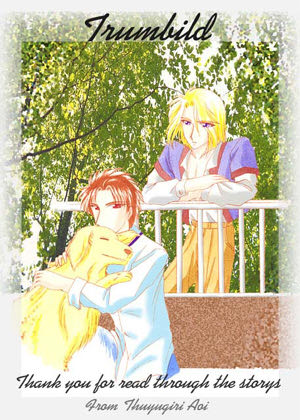
|
|
|
|
|
第四話 はじまりの言花
赤炎聖騎士団長の報告書から
見張りから報告を受けた『光の柱』を調査するにあたって、砦の守備を頼むため燐光聖騎士団長ロテールの回復を待った。数日間の待機の後、赤炎聖騎士団と燐光聖騎士団の選りすぐりの精鋭をもって目的地へ向かった。 おそらく報告された場所であろうと思われる所には洞窟が存在しており、中は透明な水晶の柱が驚くほどたくさんあった。中の広さはさほどではなかったが、中心付近に存在していたと思われる水晶柱が無惨にも破壊され破片が散乱していた。それ以外は、魔物の気配や特に目立った感触は得られず部下の言葉もあり、洞窟内の水晶柱一つと中央にあった水晶の破片のいくつかを回収して砦へ帰還した。 燐光聖騎士団長が水晶の破片を見、体力が戻り次第洞窟を検分しに行くとのことで無理をしないことを条件に、数日後再び洞窟へと向かった。洞窟の状態は以前と変化しておらず、燐光聖騎士団長が中に入って中央から外の角度を何度も測定していた。 その後砦に戻った燐光聖騎士団長によって、ようやくここ数週間にわたって起きた燐光聖騎士団長と私の不可思議な現象が推測の域をでないが説明された。 それは、『銀の乙女』とは迷信ではないかも知れないというものだ。まず私達が精神世界、『夢の世界』とでもいうのだろうか、の中で出会った少女のことは先に報告したので割愛させていただく。少女とはいえ、モンスターと判断して私が使った呪文『エリアル・フロウ』の光の柱は精神世界のことでありながらも、微妙に現実であったと思われる。なぜなら、見張りの見たという『光の柱』がおそらくこのエリアル・フロウによるものであり、光の柱が立ったと思われる付近で発見された洞窟で四散していた水晶が、我々を精神世界にとらえた少女の本体であると推定できるからだ。 ここで、何故水晶が生命を持ったかについては説明しきれない点が多い。燐光聖騎士団長の推論によると、年に数度だけ特別な日に洞窟に差し込む太陽の光が洞窟内の水晶に乱反射して中央に収束し、それによって水晶に力が宿り生命を持ったのではないかと仮定している。事実、中央に散乱していた水晶の破片はわずかながら魔力を有していると、後日到着した深緑聖騎士団長も認めている。 結果的に、『銀の乙女』というものが本当にそれであるかは断定できないが、我々が調査依頼を受けた『特定の時期に多数の行方不明者』というのは、燐光聖騎士団長と私が少女に精神世界に囚われたと同じような状況になったという解釈が最も説明がつくと思われる。 繰り返すようだが、報告としては未知数が多く断定要素が少なすぎる。今後は水晶の洞窟の調査・研究を専門家にゆだねたい。
「まったく、雪に埋もれた砦は最悪だったな。おかげで二月になるまで王都に帰れなかったとは」 ぼやいているのは言わずと知れたロテールだ。 他人の執務室に来て貴族らしくなく机によりかかって何を言い出すかと思えば。 「銀の乙女に囚われたお前の責任も大分入っていると思うんだが」 たくさんある未処理の書類が見えているだろうに、邪魔をするロテールに少しムッとしながら答える。レオンはしっかり目を通してサインをするので、会話などで途中に邪魔されるともう一度見直すはめになる。そのために羽根ペンを持つ手は先刻から止まったままだ。 「あの娘は可愛かったからいいんだ。それより、マリア様と深緑聖騎士団が来たってことのほうが大変だった」 「何だよ、それは。お前が死にかけたのを気づかって、マリア様は雪深い中をわざわざ来て下さったんだぞ。当然、一個師団は護衛につくからマハトは仕方なかったとしても……」 「まあ、普通なら回復に三週間以上かかるところが二週間で済んだけどな」 「嬉しくないのか? マリア様にずっと看病してもらってただろう」 「それが一番つらかったんだよ」 マリア様のこととなると、ロテールはめっきり歯切れが悪くなる。そういえば砦に居たときもマリア様がいると口数が減っていた。看病しているからと優しく言われて、ロテールをマリア様に任せてマハトと銀の乙女に関する調査を続けていたため、滅多に会うことがなくなっていたが。 「聖乙女が嫌いなのか?」 「聖乙女というより、マリア様の感じが……な、苦手だ」 溜息をついて答えたロテールが、書類に手をのばす。最近暇があればここに来てレオンの書類整理の手伝いをしてくれるようになっていた。目を通さなければならない重要なものと、サインだけすればいいものにわけてくれて、重要なものにだけ目を通すよう指示され半信半疑でそうしたら、いつもの二分の一程度の時間で済んでしまって驚いた。『お前は要領が悪いんだよ』とロテールは言うが、そうそう自分を変えられるわけはなく、ロテールがいないときのスピードはやはり遅くて少し情けない。 それだけに、要領の良いロテールにも苦手なものがあると聞いて少し意外に感じてしまう。 「女は得意なんじゃないのか?」 「マリア様は何故か、な。こういう感情って言うのは自分でもどうしようもないときがあるだろ」 「そういうものなのか?」 「そういうものなの。俺がお前を好きだって思う気持ちと同じだ」 いきなり言われて目を瞬かせる。言った本人は悪戯っぽく微笑んでいるだけだ。 どう答えればいいのか、困る。なんとなく持っている羽根ペンを手持ちぶさたにいじってしまう。 「……よく、わからない」 「理屈じゃないからな、教えてくれと言われても説明できないぞ?」 楽しそうに言うロテールの瞳をじっと見つめる。相変わらず菫色の瞳は優しい光をたたえていて、困惑する。その輝きからレオンは目をそらせない……。 「お前が……言っていることが本気だっていうのはわかる、と思う。でも、やっぱりわからないんだ……俺は恋とか、好きになるってことから遠いところに今までいたから……俺は、どうしたらいいんだ? お前は俺にどうして欲しい?」 うまくまとまらない考えをそのまま素直に話す。自分で言っていてもやはりわからないし、これでは聞いているロテールの方はもっとわからないのではと思う。 すると、ロテールが今までのからかい半分とは全く違う淡い微笑みを浮かべた。 「そういうことを言うと、俺はお前にもっとわがままを言いたくなるぞ?」 「え? 何で?」 きょとんとして問い返すレオンに、ロテールはふっと目を細める。 「お前はお前のままでいいんだよ……変わる必要なんて全然無いんだ。人を愛することを知っているお前は変わらないまま人を好きになれるさ。それが俺に言える、もう一つのヒント」 「知ってる……って、え?」 言われたことを理解できずに戸惑う。それが面白いのか、混乱のタネをまいた張本人はまた悪戯っぽく笑ってレオンに顔を近づけた。 「そして、その心を俺の方に向けてくれるとなおいいんだけどな」 「は? ……あ、あのなあ」 さすがにこれにはあきれる。 ふざけ半分で言ってはいたが、それがロテールの本心からなのだとわかるが。
執務室の扉がノックされてロテールが呼ばれる。 「何だ? 急務か? 折角ヒマになったと思ったら」 息をついてロテールはレオンの目の前に持っていた書類を置いた。話をしていたせいで全くはかどっていない仕事は、いつのまにかきちんと整理されている。 「そういうわけだから、後は自分で頑張るように。あ、そうそう先刻のこと、わからないなら身近な人にでも聞いてみるといいぞ?」 「え……? おい」 レオンは言われたことに思考が追いつかずに聞き返す。 部屋を出る寸前、こちらを見たロテールの瞳はあの優し気なものではなく。とらえきれない光を宿していて……。 「身近って……ロテール!」 誰のことなのか限定しないままではわからない。しかし、すでに閉じられた扉の向こうから答えは返ってこない。 (マハトにでも聞けってか……?) 穏やかで気安く話しかけられる友人……今や同じ団長同士だが、こういう話を聞いても良いものか悩む。 時を告げる鐘が鳴る。 「あっと、約束があったんだっけ」 我に返って、机上の書類をしまおうかと手を伸ばす。が、指が触れる寸前で手を止めてしまった。ため息をついて立ち上がる。 約束を破るわけにはいかない。どうにもならない考えを無理矢理どこかにやってしまいたくて、部屋を後にした。
先にレオンの執務室から出たロテールは、扉を閉める直前に尋ねたレオンの言葉を聞いていた。相変わらず人の気持ちにはとことん鈍いレオンに、深く息をつく。悪気がないのは十分承知しているし、それがレオンだというのも良く分かっているのだ。変わって欲しくないのに、変化を望んでいるその矛盾は自分のわがままだというのも理解してはいる。 しかし……。 「さすがに、この状態はつらいな……」 いつまた自分自身を止められなくなるか、わからない。今のままでも十分ぎりぎりのラインで押し止めているのに、レオンはそれを少しも分かってはいないのだ。 そして、さらにロテールを追いつめる行動を取っているということが、分かっているのだろうか? 自分の執務室の扉に手をかけたまま、レオンの執務室の方を見る。騎卿宮の廊下は人気が全くなく、窓から差し込む光があっても辺りが暗く感じる。 「やはりお前はあの、何も知らなかった頃の方がいいのか……?」 銀の乙女らしきものがいた精神世界で、自分が着ていた服。レオンと出会ったときの夜会の正装だったのは、それがレオンの中で一番印象に残っているということだ。夢も精神世界も自分を映す鏡のような世界。あの時意識が無かったロテールより、レオンの心を映す世界であったことをロテールは知っている。純粋さをあらわすかのような白い世界は、レオンそのものであったから。 つぶやいた自分の言葉に、さらに気分が沈む。急務の書類にも目を通す気が起こらず部屋のソファーに座る。 「あとで気分転換にでも、行くか……」 何かをしていないと、気が狂ってしまいそうだ。 時を告げる鐘の音と共にロテールは書類に手をつけた。
砦から帰ってきた数日後のこと、馴染みの酒場で食後のお茶を飲んでいたら、呼び出されて人気のあまりない通りに向かうことになった。相手はこちらを見て駆け寄ってきた見知らぬ女の子だった。 何かと思ったら、知人の名を出されて驚く。それは、自分の騎士団の副団長だった。話を聞こうと尋ねたら、いきなり涙をこぼされて困り果ててしまった。どうにか彼女を自宅まで送ることができた。その後、礼と共に相談したいことがあると言われて再び彼女と会うことになった。 落ち着いた様子の彼女は先日のことを詫び、事の次第を話してくれた。 どうやら、彼女は副団長の恋人らしい。だが、喧嘩をしてしまったまま任務に行かれてしまい、仲直りするきっかけがつかめないというのだ。 それを聞いて、自分などで役に立つのか正直疑問がわいたが、話し相手にだけでもいいからと今にも泣きそうな顔で懇願され、ついうなずいてしまった。忙しくて会えるのはたまではあったが、自分が見た限りの副団長の行動や様子を話すだけで嬉しそうにしている。『本人に直接会った方がいいのに』と言ってみたら、悲しそうに『会う勇気がまだないんです』と言われてしまってまた困る。 ただでさえ、女の子と付き合うことになれていないのでどうしたらいいのかわからない。他にも問題はあるのに。
「あの、さ『恋』とか『好き』ってどういうことなのか説明できないかな?」 酒場で食事をしているときに女の子にふと尋ねてみる。自分で考えていると同じ所を堂々巡りしているので、きっかけが欲しかった。ロテールの言っていることは難しすぎて完成しないパズルのようだ。 「恋、ですか? どうしたんですか、急に?」 「いや、その……どういう風に思うことが『好き』になるのか、それが『恋』になるのかってよくわからないから……君ならわかるかなあって」 肩くらいまでの茶色の髪を揺らして小首を傾げる相手に、わかるように話す。少女はまるで妹を見ているかのようで話しやすい。 「うーん、そうですねぇ……まず第一印象かなぁ? ぱっと見て、あ、この人いいなって思うんです。その時は『好き』ではなくて『気になる』程度なんですよね。たびたび出会ったり見かけたりすると、その人について友達に話してみたり。それで、ふとしたときに改めて見ると、ドキッとするんです。それが『好き』になりはじめたことの証拠かな? 出会うたびにドキドキして、話しかけてみたいけど怖いなって思ったり……相手が友達だったりすると、そういう感情を隠すのが大変で……そこから勇気を出して話しかけてみて笑ってもらえたりすると、好きなんだなぁって自覚できて、それで『恋』になるんだと思います。告白とはまた別……だと思いますけど」 にこにこ笑って話してくれるその内容は、具体的でわかりやすい言葉であった。良く聞くこういう話のことは今までさっぱり理解できなかったが、今回のことで少しは分かったような気がする。今の自分の気持ちについてゆっくり考えてみようと思い直して、目前の少女に笑いかける。 「ありがとう、とても参考になるよ」 「いえ、そ、そんなこと……ただでさえお忙しいレオン様の貴重な時間を割いていただいているのに、お礼を言われるほどのことじゃないです」 控えめに微笑んで返してくれる彼女は、いつもより顔色が良くなった気がした。会うときのほとんどが悲しそうな表情なだけにホッとする。 「とりあえず、そろそろ戻ってもいいかな?」 「あ、はい。いつもすみません」 席を立つ自分を戸口まで送ろうと少女がついてくる。酒場を出ようと扉の側まで近づいた時だった。 「!」 今入って来ようとした人物……ロテールと思い切り目が合った。 「よぉ、レオン。そちらの可愛い彼女とデートか?」 いつものような笑顔での挨拶。だが、それが本当に心から笑っていないと思ってしまうのは、瞳に宿る光が全く笑っていないからだ。つい、一歩後ずさりしてしまう。 「ろ、ロテール様! デートだなんて、誤解されるようなこと言わないで下さい!」 隣にいた少女の方が驚いて、ロテールに返した。 「男と女が一緒にいたら、やっぱりカップルだと思うぞ?」 「レオン様にはお話を聞いてもらっているだけです! ご迷惑をおかけしているのは十分わかっているんですが……」 ロテールがからかうように女の子に向けた視線で、動けなくなった体が少し動くようになって助かる。しかし、今度は少女の方の言葉がだんだん力がなくなっていくのに気付いてレオンはあわてる。せっかく元気になったと思ったのに。 「俺は迷惑だと思っていないから! 君の勇気が出るまで話を聞いてあげるよ。だから、泣かないでくれ! ……ロテール、どうしてそういう言い方しか出来ないんだ!?」 うつむいてしまった少女に出来る限りの言葉を言ってから、ロテールをにらむ。 見つめた瞳は。 淋し気な光が揺れていた。 はっとして、何かを言おうとしたが言葉が出てこない。 「はは、すまない。悪気はないんだ、許してくれ」 表情は笑っていたが、声にいつもの精彩が無い気がする。 「いえ、すみませんこちらこそ……悩みがあってすぐ泣きたくなっちゃうんです。自分でも、どうしたらいいのかわからなくて……」 「恋する乙女というのはそんなものだろ? まあ、がんばれよ」 「ありがとうございます」 ロテールが女の子の肩に手を置いて励ますのを見ていて感心する。 少女は少し前とはうって変わってはにかんだように微笑んでいた。自分ではとてもできない。 「じゃあ、な」 「あ……ロテール?」 「何だ?」 もう興味はなくなったかのように酒場に入って行こうとするロテールに、はっとして呼びかける。先程の淋しそうな感じを聞こうとしてどう聞くべきなのか迷う。 「いや、その……なんでもない」 「? それならいいが」 歯切れの悪いレオンに首を傾げてそれ以上追求することなく、ロテールは再び別れを告げて去っていく。その背中を見つめていると。 「レオン様? お戻りにならないと……」 「あ、そうだった。じゃあ、また」 指摘され少し照れ笑いして誤魔化して、騎卿宮に戻った。
手元に残っていた書類を片づけると、今日の仕事はほぼ終わった。 いつもならこの後、武仰殿にでも行って剣技の修行でもするのだが。今日に限って何もやる気が起きずに、机に肘をついてぼんやりと視線をさまよわす。 仕事だと割り切っていたつもりだったが、書類に目を通しているときも先刻のロテールの様子が気になって頭からはなれなかった。 一瞬よぎった哀しそうな色彩。気のせいではなかったはず。 なんでこちらを見てそんな表情をしたのか、考えても答えは出ない。 どれくらいぼんやりしていたのか。時を告げる鐘にはっとする。 「……あいつのことなんか俺には関係ないのに……何やってんだろ、俺……」
過日の遠征に対する報告会が開かれた。 十二月下旬から二月はじめまで王都を不在にしてしまった聖乙女と赤炎・深緑・燐光聖騎士団。厳しい冬の寒さのため他国の動勢はそれほどでもなかったが、王都の民を不安にさせてしまったのは事実である。その分報告書は山のように提出した。 概要をはじめに提示して、説明がはじまる。 体験したことをそのまま言葉にしているだけなので、あまり話に意識が向かない。質疑応答まで相当ヒマを持て余すことになりそうだ。 レオンはふとロテールの方に目を向けてしまう。 今回の遠征の責任者であるが故に、話をしているのはロテールであった。いつもの調子で要点をわかりやすく説明していく。それでも全ての説明をするのに一刻ほどかかってから、ようやく会議らしいものになった。 自分の体験してきたことを尋ねられるままに答えていく。報告書に全て書き上げてあるので、それは確認ということだ。 だいたいそれぞれの納得がいくところまで話をし、質問が無くなって報告会が終わったのはゆうに三刻以上過ぎていた。
ずっとにこやかに対応していたロテールは、書類の束を整えながらため息をついた。 「すまない、ロテール」 「何だ、急に?」 「俺も事件の当事者なのに、お前ばかり矢面にたって説明しっぱなしで……」 レオンが話したことなど、形式上の確認作業ばかりだ。ロテールの負担は相当なものだったろう。 「今回の遠征は俺の担当だったから、当たり前だろ? お前が気に病む必要はないさ」 優しい言葉ではあったが、何、か……いつもとは違う感じがしてレオンは眉をひそめる。何が違うのか、書類をまとめて立ち上がったロテールを見てふと気付いた。 紫の瞳がこちらを向かない。 「ロテール?」 「ん?」 一応、こちらの問いかけには答えてはくれるが視線は合わせず、何を考えているのかはわからない。 「もう、皆執務のために騎卿宮に戻ったぞ。お前も行かないと書類の処理が終わらなくても知らないからな」 確かに、会議室にはレオンとロテールしか残っていない。今回の『銀の乙女』の報告は、たとえ断定できない未確認の情報だったとしても出席した人たちの好奇心を刺激しただろう。詳細な報告書はこんなところで読めるほど単純なものではないから、各々自室にすぐさま戻って行ってしまったのだ。それはレオンも当事者でなければ同じ行動を取っていただろう。
そんなことは、今はどうでもいいのだ。 からかい半分に言ってもなおこちらを見ないロテールに。 怒るよりどうしていいかわからなくて、身を翻しかけたロテールの腕をレオンは思わずつかんでしまっていた。 「! どうした、レオン」 引き戻される感覚にロテールが驚き、振り向いて合わさる視線。 いつもと違う感覚をなくそうとしたことで取った行動が、完全に自分の意志からかけはなれてしまっていて、レオンも困惑する。 鮮やかな紫から目が離せない。 何も言わないレオンに、ロテールは少し困ったように微笑んだ。 「……どうしたんだ? 何か言いたいんじゃ、ないのか?」 ゆっくりと尋ねられて、はっとレオンは我に返る。何かと言われても、自分でも理由のわからない行動を取っていることがすでに分かっていない。 「え、っと……」 言いよどむこちらに彼は苦笑いする。瞳に以前見た淋しそうな光が煌めく。 「俺と一緒にいると、彼女に変に思われるぞ?」 「え……? 何だ、彼女って」 「…………おい?」 言われた言葉の意味が分からなくて聞き返したら、ロテールがあきれたように尋ね返してきた。 「彼女……って誰のことだ?」 「……レオン? お前、酒場のところで一緒にいた彼女と付き合っているんじゃないのか……?」 「つきあ……って、ってはあ!?」 「花街の方でも噂が流れている位だぞ? 恋人かって」 どこをどう取ったらそうなるのか。噂というからには別にロテールだけがそう思っているというのではないだろう。 「こ、恋人だなんて、それこそ誤解だ!」 そう言い切って、はっとする。よくよく考えてみれば、受けた相談内容自体は周囲に秘密にして欲しいと言われていた。 「そ、そうか。彼女の悩みを聞いて勇気付けてあげようと思ってたけど、まわりから見たら……」 それこそ、恋人同士語り合っていると思うだろう。別に本人たちにその意志はなくともいつでも周囲の人間はそう決めつける。一回だけならまだしも、ここのところヒマさえあれば会ってあげていたのだから、なおさらだ。 「……お前って……」 どうしようもないと言いたいのか、それ以上で言葉すら出ないのか、ロテールはため息をついた。 「つまり、どういうことなのか、はじめから説明しろ」 ほとんど脅迫に近い雰囲気で言われて、結局事の次第を教えてしまうことになった。
「彼女もまあ、相談相手を間違えたものだな」 「悪かったな」 会議室にあるテーブルに、腰掛けてつぶやいたロテールにむっとする。 そんなこと、言われるまでもなく自分が良く分かっている。秘密だと言われていたことを話すのにためらっていたら、本当に脅された。椅子に座って話をする、という和やかな感じではなく、壁に背をもたれて精一杯ロテールをにらむ。 「女の子の秘密だから最初に言ったとおり、絶対他人には話さないよ。だから、そんなに拗ねるな」 「怒ってるだけだ」 なだめるように言われても、やはり約束を破ってしまったことには変わりない。 「隠していたって、お前にどうにかできる問題じゃないと思うがな」 痛い所をつかれて言葉に詰まる。相手の笑い顔がいつも以上に気に触る。 「言ってくれれば、上手に立ち回ってやったのに。まったく……このままだと彼女、お前と付き合っているってことになって、元の男と仲を戻す事なんて出来ないぞ」 「……それは……じゃあ、お前だったらどうするんだ」 「俺? そうだな。まず、その相手の男に会うな。話を聞いて、どう思っているか聞く。両方から話を聞くことが大事だ。で、そのうち落ち着いたらそれとなく二人を会わせてやるってのが基本かな」 「へえぇ……だてに女遊びはしてないな」 「……お前がものを知らなさすぎるんだ。特に恋愛関係について」 あきれたようにロテールがつぶやいた。その言葉の奥に隠された想いはレオンには届かない。 「どうせ……」 「そこで拗ねるところがまだまだだってことさ。ま、その件は俺が何とかしてやるから、お前は横で見ているんだな。少しは勉強に……なるわけないか、レオンだもんな」 「なんだよ、それはっ」 からかうように笑って決めつけたロテールに、レオンが反応する。そのままロテールを殴って、レオンは会議室の扉の方へと向かっていく。 「……そういうところが、良いんだけどね」 「? 何か、言ったか?」 つぶやいたことに気付き振り向いたレオンは、寸前まで怒っていたのを忘れたかのように尋ねた。 その様子に微笑んで。 「いや、なんでもない」
「ロ、ロテール! どうしたんだ、その頬!?」 レオンが慌てるのも無理はない。 ロテールの白い顔の左頬が赤くなっていたからだ。 「いやぁ、見せつけられてしまったよ。邪魔者役は体を張らないと」 「邪魔者役……って」 楽しそうに笑う相手にレオンは困惑する。 今日は問題のカップルを対面させると言っていたので、酒場でこうして待っていたわけなのだが。どうなったのか聞くよりも前に、顔のアザに目がいってしまった。よく見るとそれは手の形にも見える。 「カンタンに言えば『彼女を横取りしてやるよ〜』って男の目の前でいってやったのさ。とても、効果的なシチュエーションを加えてね」 「それは……」 確かに効果的だろう。しかも、相手はロテールだ。噂など無くとも信じてしまうかも知れない。 「おかげで殴られ損だが……女の子の泣いている姿は見たくないしな」 「大丈夫だよな、あの二人……」 「喧嘩する前以上に仲は良くなると思うがな。後は二人次第だ」 ふっと視線を扉の外へ向けたロテールにつられてレオンもそちらを見る。 もう暗い夜の色に包まれた世界は、全てを同化させて人の姿も何もかも見えはしない。 そちらを見つめたままのロテールの顔に目を移す。 端正な面立ちは派手な噂さえなければ、物憂げな詩人のようだ。 「ありがとう、ロテール」 「……別に。これくらいお安いご用だ。礼などいらないさ」 見つめ返して自分に向けてくれる優しい微笑みに見とれてしまっていると、ロテールが席に座らずに酒場を去ろうと動いた。 「どこへ行くんだ?」 「散歩」
夜はさすがにまだ寒い。春に近づいてきたのでだんだんと暖かくなってはいるのだが。 月明かりの下、前を歩くロテールの背中だけを見ている自分がいる。 銀の乙女の一件からは、側にいるだけで特に何をしたというわけではない。こちらの質問には優しく答えてくれる以外、前と変わらない。どうしてなのかは分からないが、その分考える時間が増えていた。少女の教えてくれた『好き』と『恋』という感情に関すること。ロテールの想い。そして、自分自身の心。
本当は、もうわかっているのかも知れない、その答えを。
最近そう思うようになったが、はっきりとしたことは言えない。自分の中にある言葉だけでは説明しきれなくて。
「あの花……! こんな時期に咲いているのか」 「え?」 感嘆する声にロテールが立ち止まっている事に気付いたレオンも足を止める。 あげた視線の先に広がるのは、夢幻の世界。 月の光に照らし出されて、木の枝にこぼれるばかりに咲く白い花の輪郭はぼやけて一層現実感を損なわせる。 「これ……は」 「お前と会ったときに咲いていた花だな」 覚えている、しっかりと。あの時は、まだお互い誰なのかも知らなくて。 一年前と変わったのかも知れない。変わらなかったのかも知れない。 だが、目の前に咲き乱れる花の美しさはまったく変わっていなくて……。 離れたところにいても優しい香りがふんわりと辺りに漂う。 二人して何も言わずにその光景に見入ってしまう。 「気のせい……か?」 「ロテール?」 ふとつぶやいたロテールが、足早に花の方に向かうのに遅れてレオンが声を掛けるが、立ち止まる気配はない。 慌てて、後を追う。 満開に咲き誇る白い花弁が舞う景色は夏の緑の木陰とまったく異なり、すがしい香りをもって世界を圧倒している。 真白に輝く世界にロテールが足を踏み入れたとたん、一陣の風が吹いた。柔らかく、暖かく感じるそれは夜の冷たい空気を一掃するかのように強く通り過ぎ、花びらを散らせる。 踊るように舞い散る花弁が、ロテールの姿を覆い尽くす。 「!」 あたかも雪のように降り注ぐ花びらの乱舞は、月光によって辺りを乳白色に染め上げる。 まるで、世界の全ては夢だと言うかのように……。 瞬間、レオンの全身に激痛が走った。いや、こころに、かもしれない。 色々な考えや想いが渦をなしてつかめなかったはずのそれが、意識を押しのけてレオンを動かした。 「ロテールっ!」 甘く香る白い世界に駆け出す。 頭の中が痺れるような感覚で、それが一瞬だったのかとても長い時間だったのか、それすら分からない。 見えない彼の影に怖くなって伸ばした手は。 ロテールによって優しくつかまれて、引き寄せられた。走っていた勢いが殺せないままに抱きつく。 「どうした、レオン」 驚いて問いかけられる声が心に柔らかく染み込んでいく。 知らず涙が零れた。 「こわ……かった……ロテールがいなくなったかと……」 まだ不安が抜けきれず、強くすがりつく。そうしている相手がロテールじゃないと言われたら、死んでしまうかも知れない。 すがりついてなお小さく震えるレオンの背をなだめるようにそっと撫でて、ロテールは囁く。 「お前を置いて、俺がいなくなるわけがないだろう……どうして欲しい? どんな言葉が欲しい? お前の言うことならなんでもしてあげるから……落ち着いて、話してくれ」 何かに怯えるレオンを救いたくて、紡ぐ言葉すらもどかしい。 不安を取り除ける力が自分にないことがたまらなく腹立たしい。 こんなに側にいるのに遠い存在。 狂おしいまでのこの想いを心の奥に閉じこめてさえなお、止められない自分がいる。 その器をとらえて籠の中に閉じこめてしまえば、こんな不安などなくなるに違いない。 だがそうしてしまえば、レオンという存在はあの輝くばかりの光を失ってただの骸と化すだろう。 欲しいのは、そんなものではないのだ。 自然であって欲しいと願う心も、真実。 あれから避けているのは良く分かったが……せめて少しでも側にいられる時間が欲しかった。 どんなに偽善だと言われてもいい。愚かだと笑われてもいい。
本当は、目の前の存在に嫌われたくないのだということ。 ただ、それだけなのだ。
突然飛び込んできて、そのまま動こうとしないレオンに戸惑う。 抱きしめていることで震えが収まっていくのはよくわかったが、何が起きているのか、ロテールはつかみきれていない。 「レオン……」 体の震えが止まってしばらくして、耳元で優しく名を呼んでみる。すると、レオンが小さく反応した。やがてすがりつく腕の力がゆるんだので、そっと体を離す。
間近で見つめ合う、菫と落日。
顔を上げたレオンの瞳は涙で潤んでいた。 本人は気付いていないのだろうその艶っぽさに、ロテールは息を呑む。 目の前の躰を強く抱き寄せ、自分のこと以外のいっさいの思考を奪い取り、存在がここに在るということを確かめ、全てをあますことなく愛したいと思う自分を必死に押しとどめる。 「黙っているだけじゃ、わからないぞ……?」 内心のあさましい考えを悟られまいと微笑む。 想いを寄せる相手は、そんなことなど考えもつかない程純粋な心の持ち主で、昏い考えを持つ自分に嫌気がさす。
考えるより先に思いの力によって動かされ、ロテールに抱きついてしまったレオンだったが。落ち着くまでなだめてもらってもなお、心は震え続けている。 躰に心地よく響く声にうながされて、顔をあげる。優しい光を宿す紫の瞳は、今この淡く浮かび上がる白の世界で自分だけを映している。それだけで鼓動が早くなる。 ロテールと触れ合っている部分が、服を通してもどうしようもないくらい熱く感じる。 思考はすでに、何も考えられなくなっている。
「俺は……」 「ん?」 穏やかに微笑むロテールを見つめたまま、迷わず口をついて出てきた言葉は。
「お前が、好きなんだ……」
「……え?」 瞬間的に言われたことが理解できずに目を見開く。時間差で言葉が心に染み込む。 「レ……オン?」 「多分……いや、きっとこれが『好き』ってことなんだろう……今でも良く分からないけれど」 驚いた表情を崩せないままのロテールに、はにかむように笑って甘えるように自ら躰を寄せる。 ロテールはレオンを無意識に抱きしめて、その後に自分の取った行動に気付く。 「レオン……」 茫然とした声のままのロテールに、レオンは顔を寄せたままクスクス笑う。 「これでも、ちゃんと考えたんだぞ? 俺が人を愛するってことを知っているっていうところまではまだ結論がでないけど」 あまりに唖然とし過ぎていたのが悪かったのか、レオンが拗ねるように上目遣いでロテールを見た。 その様子にゆっくりと、しかし鮮やかにロテールは微笑んだ。 「嬉しいよ……レオン」 「ロテール……」 もうそらされることのない紅玉の瞳を愛おしむように、顎に手を掛け焦らすようにゆっくりと唇を奪う。 一瞬だけ小さく震えた躰を逃がしたくなくて、強く抱く。
「んっ……」 今まで交わしたどれよりも甘く感じる接吻に意識が奪われて、どのくらいそうしていたのか分からない。 口づけから解放されて、間近にある紫の瞳を見つめる。 辺りを春を告げる暖かい風が緩やかに通りすぎた。 一斉に花弁が散り、甘く芳しい薫りがむせるくらい濃くなる。 風によって頬を叩く自らの髪に気付き、辺りに視線を向けたロテールと同じように辺りを見る。 「あ……れ? 色……が」 「ああ。白から薄桃色になったな……」
それは、とても幻想的な光景だった。 大地を覆う花弁は、月明かりでぼやけた白。木々の枝に競うように咲き誇る花々は、薄桃色が夜空の暗さにくっきり映えてとても綺麗だ。 「まさか今、このときに色が変わるなんて神様も気が利いてる」 神様なんて、信じちゃいなかったが、とロテールが感嘆したまま呟く。 「何が……? どういう意味だ?」 「この樹は伝説によれば、数百年に一度……突然花の色が変化するらしい。しかも、それは樹の名が象徴する言葉に相応しく、恋人達を祝福するために変わる」 「そんな伝説……あるのか? 樹の名前ってなんだ?」 接吻の余韻から抜け出せず、ぼうっとしたままの表情で尋ねてくるレオンに、ロテールは微笑んで頬にそっと唇を寄せる。 「お前も良く知ってるし、食べたこともあるよ。これは……巴旦杏さ」 「え? アーモンド、なのか? これ……」 耳に掛かる息がくすぐったくて体を無意識によじると、抱き締める力が和らいでロテールの顔が正面に見えるようになった。 目を見開いて驚くレオンに、ロテールが視線を戻して淡く微笑む。 「そう……何故、この名前を出会ったときに思い出せなかったのか……。今なら良くわかる」 そういえばあの時、ロテールは知っていた筈なのに忘れたと言っていた。料理などでよく見かけるその名を思い出せなかったとはどういうことなのだろう。 「そんな特別なものじゃないのに、花の色が変わるなんて……不思議だな」 「俺達を祝福しているのさ」 ロテールのいつもの調子良い台詞に、レオンが小さく笑う。それを見咎めて。 「本心から言ってるのに、信じてないな」 こちらを見つめる炎のような瞳に惹かれるように、ロテールは頬に手をあてる。 暖かいぬくもりを伝えるそれに、レオンが甘えるように頬をすり寄せた。 「だって、他の女の人にも同じようなことを言ってるんだろう」 「お前の目前にいるときは、俺のこの唇から出てくる言葉は真実だよ。わかってるんだろ? レオン」 「わかってるって……」 はっきり言い切られて困惑する。 ロテールの言葉を疑うわけではないが、自分の心もまだつかみきれていないのにどうしてそう思えるのだろう。 心の揺らめきを瞳の中に映してこちらを見るレオンに、ロテールは微笑む。 「じゃあ、俺が嘘を言っているかどうか確かめてくれよ」 「えっ……」 何かを言いかけたレオンの唇を優しく塞ぐ。 「ん……ふっ……」 「……お前だけが、俺の真実だよ……」 接吻から解放して、ほんのりと頬を染めているレオンに甘く囁き掛けて優しい微笑みを浮かべると、ロテールはレオンから離れて右手を取ってひざまずく。 「ロテール?」 「この花の名に誓うよ……この俺、ロテール・アルヌルーフ=リング・テムコ・ヴォルトの全てはお前のものだと……」 囁くように言って、レオンの右手の甲に口づけをする。 薄桃色の花びらが舞い落ちている中で。
「巴旦杏の名が象徴するのは『永遠の愛』……その名にかけて……お前を愛するよ」
|
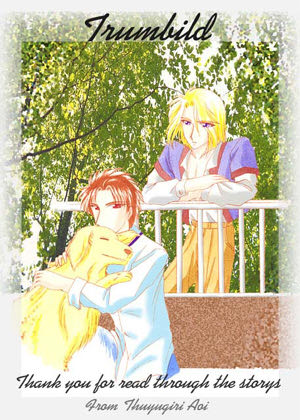
END■