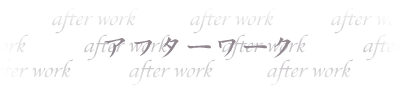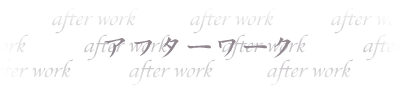|
仕事があった日の帰りは、必ず外から自室の窓を見上げる。
自分でも気づかないうちに、身に付いた習慣。そうして窓を見上げれば、自分ひとりしか住んでいないはずの部屋には、必ず明かりが灯っていた。
帰るべき場所を包む明かりを見るたびに、ほっとする。「おかえり」と言ってくれる人の存在を感じるとともに、でも心のどこかが警鐘を鳴らしている。
ひとりに慣れるのは大変だ。だが、誰かがいることに慣れるのはたやすい。一度思い出してしまった孤独の痛みを再び忘れることは、難しかった。
わかっていても、心は部屋から洩れる光に安堵する。人のあたたかさを知ってしまえば、やはりそれを自分から切り捨てることはできなくて。
いつものようにほのかな明かりを確認してから、壬生紅葉はマンションのエントランスをくぐった。
*
「お、帰ってきた。おかえりぃ、邪魔してるぜ」
鍵を開けて部屋に入ると、奥から呑気な声が聞こえてきた。
コートを羽織ったまま、廊下を抜けてリビングを覗く。一人暮らしにはいささか広すぎるリビングの真ん中で、緋勇龍麻が座り込んだままひらひらと手を振っていた。
龍麻はいつも、そこにいる。壬生が留守の間に勝手に上がり込んでいるくせに、家中の電気をつけて回るだけで他のものには一切触れようとしない。テレビもつけなければソファにも座らず、いつでもフローリングの床にそのまま座り込んでいた。
「俺、床が好きなんだ」
何度室内のものは自由に使ってもかまわないと言っても、ケロっとした顔でそう頑固に言い張るだけなので、壬生ももう諦めている。本当に床が好きなわけでは勿論なくて。おそらく目の届かないところで他人に自分の物を触られるのをよしとしない壬生への心配りなのだろう。
それを裏付けるように、壬生が帰ってくれば龍麻はむしろ傍若無人と言える程度には好き勝手くつろぎはじめる。その見事なまでの態度の違いは、いっそ感心するほどだ。
もっとも、その気を使っているのかいないのかよくわからない部分が龍麻の魅力でもあり、老若男女問わずに慕われやすい要因にもなっているのだろう。礼儀知らずというわけでもなく、堅苦しいというわけでもなく、どこか人をほっとさせる雰囲気は彼独特のものだった。
実際、ここは主である壬生ひとりしかいないときは、生活感をあまり感じさせないただ広いだけの部屋だ。なのに龍麻がそこにいるだけで、『帰ってくる場所』になる。彼は客人なのにもかかわらず、だ。
それだけ、僕が彼に依存しているということか。
心の中で自嘲気味に呟いて、壬生はマフラーを外しコートを脱ぐ。紺色の学生服を通して、しんと冷たい空気が肌に滲んだ。
「いらっしゃい。久しぶりだね」
「そっかぁ? そんなコトはないと思うんだけどな。あ、コラ、帰宅の挨拶忘れてるぞ」
「……ただいま」
「よろしい」
壬生のまだややぎこちない「ただいま」を聞き届けると、龍麻はにこっと笑って立ち上がる。そのまま壁際へと近づくと、壁に埋め込まれているパネルを操作した。
軽い電子音がリビングに響いて、エアコンが稼働を開始する。その音を聞いて、壬生ははじめてエアコンすら入っていなかったことに気がついた。
「龍麻……せめて、エアコンくらいは電気と一緒につけておいてもいいんじゃないのかい?」
「あ、やっぱ寒いか? まあ、そりゃそうだよな、2月って1年でいちばん寒い時だもんな」
呆れを含んだ壬生の声に振り向いた龍麻は、一瞬目をぱちくりとさせてから納得したように頷く。そのいまひとつ論点のずれた反応に、壬生は脱力しそうになりながらも脱いだばかりのコートとマフラーを龍麻の頭の上に落とした。
「うわっっ、何すんだよ!」
一方いきなり厚手の布の山に視界を塞がれてしまった龍麻は、しばらくの間ばたばたと暴れてなんとか布の隙間から顔を出すと、こんな目にあわせた張本人を睨み付ける。睨み付けられた壬生は壬生で、つい無意識のうちにため息をもらしてしまった。
「僕じゃなくて君のことだよ。いくら建物の中といっても、冬は冷え込むんだ。ほら、家の中にいたっていうのに、僕より冷たいじゃないか」
「俺、別に、寒いの平気なんだって」
「で、夏になったら暑いのも平気だって言い張るのかい?」
「う…………」
どうやら、図星だったらしい。
ああ言えばこう言う、ある意味とてつもなく口が達者でへりくつをこねるのが得意な相手をめずらしく黙らせたのが満足したのか、壬生の口元に柔らかい笑みが浮かぶ。それを認めて、反論できないまましばし不本意そうに口をへの字に曲げていた龍麻は、またコロっと表情を変えた。
「ちぇっ、なんかどんどん口がうまくなるよな、紅葉って。初対面の頃なんて無口なくせに目で語ってて、あんなにかわいかったのに」
無茶苦茶なことを言っているわりには、楽しそうに笑っている。
「おかげ様でね」
「なにー、俺のせいだってゆーのかッ!?」
「他に誰がいるんだい?」
「ちぇ……ま、い~か。やっぱ寒いな、コーヒーちょ~だい」
「……だったら、最初から暖房を入れておくんだね」
それでもいつものことながらじつによく変わる龍麻の表情にふと目元を和ませて、壬生は龍麻の要望通りコーヒーを入れるためにキッチンへと足を向けた。
*
「なんとなくに決まってるだろ~?」
壬生が拳武館の仕事をこなしてきたその日は、必ず龍麻がこの部屋に来ている。
なぜかと理由を尋ねてみたらあっけらかんとした答えが返ってきて、一瞬壬生は真面目に返答を求めたことを少し後悔した。
そんな壬生の心中を察したのか、龍麻が肩をすくめて言葉を継ぐ。決して、他意があったわけではないらしい。
「……ホントに深い意味はないんだって。偶然だろ、たぶん」
なんとなく壬生のことを考えるとわかるのだ、と言ってもきっとわかってもらえないに違いない。だから、龍麻はそう言っておいた。
出会った当初は、まさに人に懐くことなんてありそうもない狼のようだった。だけど本当は単にあるはずの感情を封じているだけだとわかったら、単なるお節介だとわかっても、今度は放っておけなくなった。
はねつけられるだろうと思って伸ばした手は、予想に反して拒まれなかった。だから、別に人嫌いじゃないこともわかった。心の奥底では、たぶん誰よりも人との交流を望んでいるのだろう。徐々に見せる表情が柔らかくなってきたと思っていたちょうどその頃、龍麻は瀕死の重傷を負ったことがある。気が付いたときにすぐそばにいたのは、壬生だった。
それ以来、龍麻は壬生が仕事の日には、必ずこの部屋へと来ている。別に拳武館の情報を握っているわけではないので、来る日を選ぶ根拠は勘以外のなにものでもない。ただ、気が向いたときに来ると、それは必ず仕事の日で。
「ん~~、でもまあ、ラッキーなのかもな。おまえって、けっこうほっとけないし」
それが、『友情』という枠を超えている感情に基づくものだということも、もうお互いが知っていることだから。
「龍麻には言われたくな……え?」
にこりと笑った龍麻がすいと近づいてきたと思ったら、壬生の視界がぐらりと傾いだ。
そのまま床に激突しそうになって、咄嗟に手を付いたらしい。龍麻の顔が、腕と腕の間にある。引き倒されたあげくに自分が彼に覆い被さっている状態にあることに気づいたときには、龍麻がいたずらが成功したときのような得意げな笑みを浮かべていた。
このままでいるべきか、それとも早急にこの体勢をあらためるべきか、壬生にはどうすればよいのかわからない。悩んでいるうちに龍麻が壬生の下から手を伸ばしてきて、壬生の頭を引き寄せ軽く抱きしめた。
「……何をしているんだい?」
けっこうな時間をかけて壬生がやっと口にすることができたのは、そんなどうしようもない台詞。
もっとも元々期待はしていなかったのか、龍麻は腕を離して壬生の頭を解放すると、明るく笑ってあっさりと言い切る。
「甘えてんの」
「・・・・・」
「……そこで、そ~ゆ~心配そうな顔しないでくんない? 別に、どこもおかしくなってね~よ」
「だったら……」
「おまえ、甘えるの下手だし。だから、かわりに俺が甘えてやるよ」
「……そういう問題なのかい?」
「だから、甘え方、覚えろよな」
「……努力するよ」
今はまだ、愛しい存在を腕の中で確かめられるだけで安堵できるから。
自分よりも少し細いだけの身体を抱きしめたまま龍麻の首筋に顔を埋めると、壬生はそのまま目を閉じた。
重なる穏やかな寝息を聞き届けたのは、窓から覗く星々だけである。
|